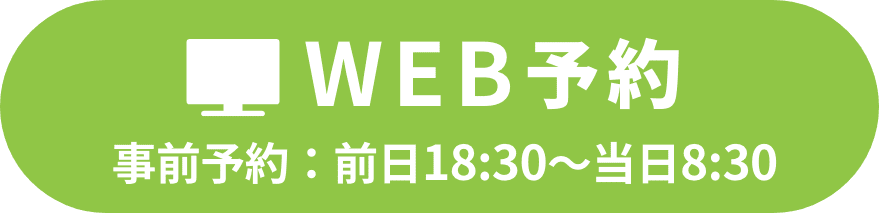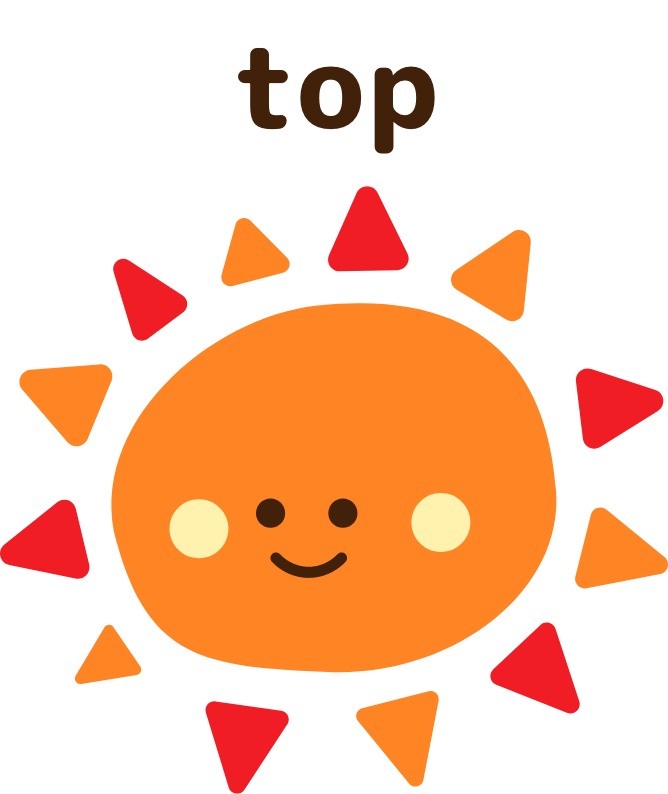今年は例年よりも早い時期から、インフルエンザが猛威を振るっており、近隣の「土山、播磨、稲美、加古川、明石」でも、インフルエンザの患者さんが増えています。
インフルエンザは毎年流行っていますが「あれってどうゆうこと?」「名前はよく聞くけど詳しくは知らない」など、疑問を持たれる方も多いかと思います。
そこで、今回はインフルエンザの疑問を、分かりやすく解説していきたいと思いますので、是非ご参考ください。
Q.インフルエンザのA型とB型の違いとは?

◆流行時期
<A型>
毎年冬の早い時期、11月から2月にかけの時期が流行のピークとなります。感染力が非常に強い点が特徴で、人・鳥・豚など幅広い動物に感染します。
<B型>
A型よりも遅れて流行することが多く、2月から春先の4月頃まで見られます。感染力はA型ほど強くはありませんが、子どもや若年層での感染が多い点が特徴であり、A型と違い「人のみ」に感染します。
◆症状
<A型>
・高熱(38~40度)が急に出る。
・全身の倦怠感、関節痛、筋肉痛が強い。
・のどの痛みや咳を伴います。
※全身症状が重い点が特徴で、高齢者や持病を持つ方が重症化しやすい傾向があります。
<B型>
・微熱や37~40度程度の発熱が続く。
・消化器症状(腹痛や下痢)が出る場合もあります。
・全身症状はA型ほど強くはないです。
※消化器症状が出るケースが多く、胃腸の不調が気になる人もいらっしゃいます。
◆予防と対策
A型もB型も基本的な予防方法は同じです。
<予防・対策>
●手洗い・マスク着用
手洗いは石鹸を使って丁寧に行い、外出時はマスクを着用し飛沫感染を防ぎます。
●ワクチン接種
ワクチンはA型B型の両方に対応しており、流行前に接種することで重症化を防ぎます。
●体調管理
免疫力を高めるために、十分な睡眠と栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。
●適度な湿度の保持
空気が乾燥すると気道粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなるため、加湿器などを使って湿度50~60%に保ちましょう。
●人込みや繁華街への外出を避ける
インフルエンザが流行している時は、重症化しやすい人(高齢者・妊婦・乳幼児など)は、人込みの外出は避けましょう。また、外出される際は必ずマスクを着用しましょう。
Q.インフルエンザの検査がすぐできない理由とは?

◆検査内容
インフルエンザの検査では「抗原定性検査(迅速キット)」が一般的となります。検査結果は10~15分程で判定できます。
◆注意点
「抗原定性検査」は、鼻やのどから採取した検体を用いてウイルスを検出するため、感染後すぐではウイルスの量が少なく、陰性になる可能性があります。信憑性が最も高くなるのは、発熱後12~24時間以降とされております。
<時間別の感度に関して>
●発熱から6時間以内:感度30~50%
●発熱から12~24時間:感度70~90%
●発熱から48時間以降:徐々に低下
抗インフルエンザ薬は、発症から48時間以内に使用することで効果を発揮するので、発熱から12~24時間のタイミングで受診し、診断するのがベストとなります。
Q.インフルエンザの治療薬はどうやって決めるの?

インフルエンザの治療薬は、「インフルエンザウイルスの量を減らすことで重症化を防ぎ、回復を早める薬」のことを指します。解熱剤のように、使用したらすぐに熱が下がるものではありません。
◆薬の種類と特徴
【タミフル】
・幅広い年齢で標準的に使いやすい内服薬(体重で容量調整)となります。
・1日2回、5日間内服します。
【イナビル】
・1回で終わる吸入薬となります。
・10歳未満20㎎/10歳以上40㎎。
・確実に吸える人が対象となります。
・気管支喘息など気道疾患の方は注意が必要です。
【リレンザ】
・吸入薬となります。
・1日2回、5日間行う必要があります。
・4歳以下の方に関しては安全性が確立されていません。
【ゾフルーザ】
・1回のみ内服します。
・12歳以上の方が対象となります。
【ラピアクタ】
・点滴薬となります。
・基本的に重症や嘔吐で内服できない方が対象となります。
以上の特徴を踏まえて、医師が発症からの時間(原則48時間以内)、年齢、症状、基礎疾患、服薬が可能か(飲めるか・吸えるか)などを総合的に判断し、家族と相談した上で治療薬を決めます。
Q.新しいインフルエンザワクチン「フルミスト」ってどんなもの?

インフルエンザワクチンとは、インフルエンザウイルスから身体を守るために開発され、感染力を失わせたウイルスの一部や、弱毒化したウイルスを体内に入れることで、免疫システムの訓練を行うものとなります。
本物のインフルエンザウイルスが侵入する前に、先に体の免疫システムに覚えさせておくことで、実際に侵入してきた時に素早く対応できるためにインフルエンザワクチンを使用します。
インフルエンザワクチンには、従来通りの「注射での予防接種」と、2024年から点鼻のインフルエンザワクチン(フルミスト)が日本でも認可され、選べるようになりました。以下に「注射」と「フルミスト」の違いを記載しておりますので、是非ご確認ください。
◆「注射」と「フルミスト」の違い
【ワクチンの種類】
■注射
・不活化ワクチン(病原体となるウイルスや細菌の感染能力を失わせたものを原材料として作られる)
■フルミスト
・生ワクチン(病原体となるウイルスや細菌の毒性を弱めて病原性をなくしたものを原材料として作られる)
【接種方法】
■注射
・皮下注射となりますので痛みがあります。
・生後6か月以上の方が対象となります。
■フルミスト
・鼻の穴それぞれに0.1mlを1回ずつ噴射します。
・痛みが無い点が特徴です。
・2歳以上19歳未満の方が対象となります。
・接種は1回のみとなります。
【効果】
■注射
・効果持続期間は約5~6か月となります。
■フルミスト
・効果持続期間は約1年となります。
※どちらも効果は同じです。
【副作用】
■注射
・注射部位の赤み、腫れ、痛み、発熱、悪寒、頭痛など。
■フルミスト
・接種後数日は鼻水や咳、発熱、のどの痛みなど。生ワクチンなので少し副作用が出やすいです。
【まとめ】

今回は『インフルエンザの疑問を分かりやすく解説』について、お話しさせて頂きました。
近年は注射だけでなく「フルミスト」という鼻に噴射するものもございますので、注射が嫌いなお子様にも簡単に行えるようになり、予防接種の選択肢も増えました!
今年のインフルエンザは、例年よりも早い時期から感染が広まっておりますので、インフルエンザワクチンの予防接種がまだの方は、出来るだけ早めに行って頂ければと思います。
また、お子様が風邪やインフルエンザなどで、保育園などに預ける事ができず、仕事も休む事もできなくてお困りの方は、加古郡播磨町にある「病児保育室 ひなたぼっこ」を是非、ご利用ください。
当施設は、体調不良のお子さまを安心して預けていただける病児保育施設となります。
播磨町・稲美町だけでなく、加古川・明石・神戸にお住いの方にも多くご利用頂いておりますので、お気軽にご利用くださいませ。
【病児保育室 ひなたぼっこ】
●住所:〒675-0151 兵庫県加古郡播磨町野添1655-1 2階
●アクセス:JR土山駅より徒歩3分
●駐車場:完備
●電話番号:078-939-6022