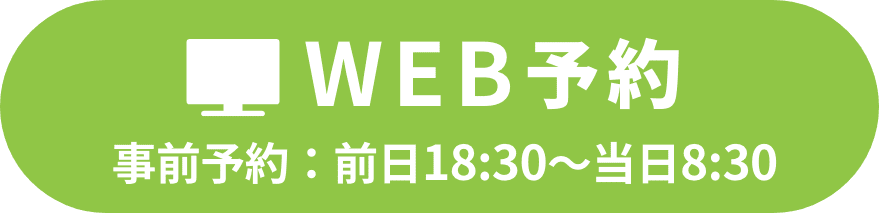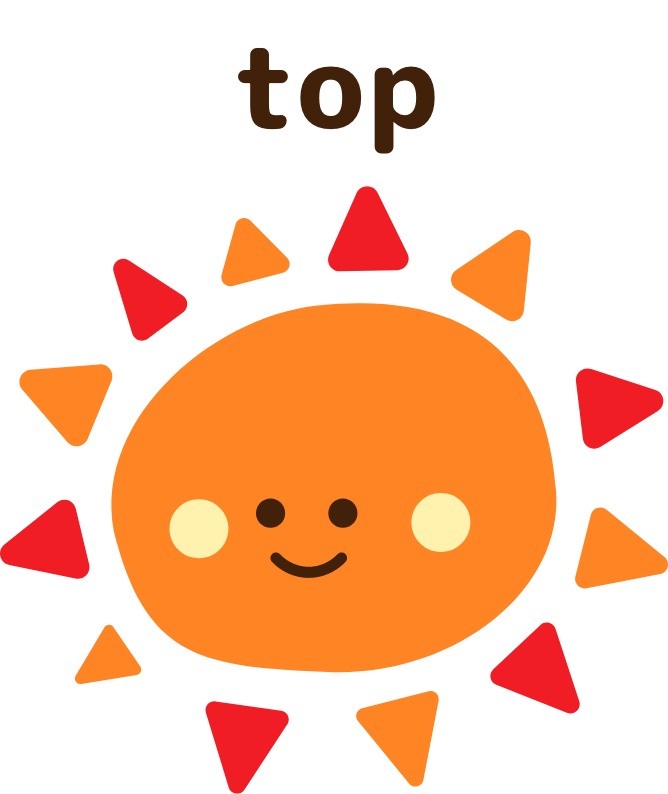私たちの体には「免疫」という、病気を引き起こす異物(例えば、ウイルスや細菌など)から体を守る仕組みがあります。
この仕組みが、ある特定の異物(ダニ、スギ花粉、食物など)に対して免疫が過剰に反応し、体に症状が引き起こされることを「アレルギー反応」と言います。
アレルギーの原因や症状は様々で、一番怖いのはアナフィラキシーです。
命に関わることもありますので、症状をしっかり観察し怪しい時は迷わず救急車を呼びましょう。
アレルギーの症状や観察ポイントなど、詳しく説明していますので、是非ご参考になれば幸いです。
【観察ポイント】

<観察ポイント>
□元気はあるか
□機嫌どうか
□呼吸は苦しそうか、ゼイゼイ、ヒューヒューしているか
□嘔吐や下痢ないか
□目や白目はどんな感じか
□発疹は出ているか
<すぐに救急車を呼ぶ場合>
●ぐったりしている時
●呼吸が苦しそうな場合
●呼吸が速い場合
●ゼイゼイ、ヒューヒューした呼吸が止まらない場合
●顔色が悪い時
●症状がだんだん酷くなっている場合
●アナフィラキシー症状がある
【アナフィラキシーについて】
咳が出る、ゼイゼイする、蕁麻疹や嘔吐など、様々な強い反応が出ており、その症状が急激に進むことを言います。
アナフィラキシーが起こる場合は、とても危険な状態となりますので、すぐに救急車を呼びましょう。
※救急車を待っている間、寝かして足を上げてあげる事を推奨しております。
<かかりつけ医を受診する場合>
●赤み、蕁麻疹があるが広がっていない場合
●アレルギー症状は少し出ているが元気はある場合
●呼吸はいつも通り変わらない場合
【アレルギー症状の分類5つ】
分類①:皮膚・粘膜症状
●皮膚の症状:赤くなる、蕁麻疹、湿疹、痒み、ヒリヒリする、むくみ
※時間が経つと消えることもい多いので、写真を撮っておくと診察の時に役立ちます。
●口の症状:口の中や喉の違和感、唇の腫れ
※食べてからどのくらいの時間で症状が出て、どんな出方をしているかしっかり観察する。
●鼻の症状:鼻水、鼻づまり、くしゃみ
●目の症状:充血、まぶたの腫れ、痒み、涙、白目がぶよぶよ
※皮膚・粘膜症状は最も多い症状ですが、必ず出るというわけではない。
分類➁:消化器症状
●吐き気
●嘔吐
●下痢
●腹痛
●血便
※何度も吐いたり、我慢できない腹痛が続く場合は危険です。胃腸症状は出方も出るタイミングも個人差があります。初めて食べた物がある日は、注意しておく必要があります。
分類③:呼吸器症状
●喉の違和感
●喉・胸の締め付け
●声がかすれる
●飲み込めない
●犬が吠えるような咳
●ゼイゼイ、ヒューヒューする
●息がしにくい
●顔色が悪い
※呼吸器の症状は命に関わるので、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。
分類④:循環器症状
●血圧が下がる
●脈が速い
●脈がふれにくい
●脈が不規則
●手足が冷たい
●唇や爪が青白い
※生命に関わる症状の為、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。
分類⑤:神経症状
●頭痛
●元気がない
●意識がもうろうとしている
●尿や便をもらす
※意識がない、尿や便をもらす状態はアナフィラキシーショックで危険な状態ですので、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。
【子どもに多いアレルギー疾患】
◆アトピー性皮膚炎◆

(特徴)
皮膚のバリア機能が低下し、痒みを伴う湿疹が良くなったり悪くなったりを繰り返す病気のことです。
子どもの頃に発症することが多く、一般的には成長と共に症状は改善していくが、成人でも1~3%の人が罹患していると言われています。
明確な発症メカニズムは解明されていませんが、遺伝やアレルギーを起こしやすい体質などが発症に関与していると考えられており、喘息や花粉症などアレルギーによる病気を併発しやすいです。
(原因)
●皮膚のバリア機能が低下することが原因で引き起こされます。
●バリア機能が低下するため、皮膚に異物が侵入しやすくなり、アレルギー反応を引き起こすことで発症すると考えられています。
●バリア機能が低下する原因は明確には解明されていませんが、遺伝やアレルギー体質などが関与しているという事も一つの原因と考えられています。
●ダニ、カビ、汗などによる物理的な刺激やストレスなどは、アトピーの症状を悪化させます。
(症状)
●多くは1歳未満で発症し、発症直後は痒みを伴い、赤い発疹が顔から首、頭皮、手、腕、脚などに現れ、1~2か月ほど経過すると、患部が乾燥して皮膚が厚くなったように変化していくのが特徴です。
●発症部位、痒みの程度などには個人差はありますが、一般的に乳児は体の広い範囲に湿疹ができることが多く、成長すると首の全面や膝・肘の内側など限られた部位にのみ現れます。
●痒みは非常に強いことが多く、患部を掻きむしってしまうことで皮膚のバリア機能がさらに低下し、アトピー性皮膚炎の症状が悪化するという悪循環を引き起こすことも多いです。
(検査)
皮膚症状の状態、発症年齢、家族歴などから「アトピー性皮膚炎」が疑われる時は、血液検査や皮膚テストを行います。
(治療)
アトピー性皮膚炎を根本的に治す方法は、残念ながらまだないので対症療法を基本として行います。
●スキンケア
皮膚を清潔にキープして乾燥を防ぐため保湿剤を使用する。
●薬物療法
皮膚の炎症やアレルギーを抑えるステロイド薬や免疫抑制剤の塗り薬を使用したり、痒みを抑える抗ヒスタミン薬などの塗り薬や飲み薬を使用します。
●日常生活
吸水性の高い肌着を身につけ、ダニやホコリなどを極力減らすといった対処が必要です。
◆食物アレルギー◆

(特徴)
●食べ物を摂取してから2時間以内に蕁麻疹が出る(大体30分以内に発症することが多い)。
●顔が腫れたり、咳や嘔吐が見られることがある。
●ひどい場合は蕁麻疹だけでなく、繰り返し咳が出る、ゼイゼイする、繰り返し嘔吐する、ぐったりするなどの症状が見られます。
●食物アレルギーが疑われる時は「何をどれくらい食べて、何分後にどんな症状が出たか」をメモしておくと診察に役立ちます。
(原因)
どの食べ物でも原因となりえるが、乳幼児期は卵や牛乳、小麦がなりやすいため、特に初めて食べる時は要注意が必要です。
※卵、牛乳、小麦は3歳くらいまでに自然に治り、半分が小学校に上がるまでにほとんどの子が自然に治ります。一方、カニやエビといった甲殻類やソバ、ピーナッツは治りにくいとされています。
(検査)
●血液検査
数値の高さはアレルギーの出やすさを表しています。数値は高くても実際に食べて症状が出なければ問題はありません。また、数値の高さが重症度というわけではございません。
●食物経口負荷試験
実際に食べてみて、症状が出るかどうかを調べる検査となります。今まで除去していたものを食べられるようになったか確認したり、どのくらいの量で症状が出やすいかを調べることが目的です。保育園・幼稚園・小学校入学前などのタイミングで、今まで食べたことのない食べ物に関してこの検査を行い、確定診断をつけることが望ましいとされています。
(治療)
●最近は食物経口負荷試験を行い、安全な量から食べ始め少しずつ増量していくことで、早く食べられるようになっていくことが分かってきています。アレルギー原因の食物でも、症状が出ず食べられる範囲までは積極的に食べることが大事となります。
●症状がでた場合は、アレルギー症状を抑える薬を飲む。
◆気管支喘息◆

(特徴)
●気管支が狭くなり呼吸が苦しくなる病気です。
●ホコリ、ダニ、猫や犬の毛、フケ、カビ、花粉などが原因で発症します。
●朝や夜、運動した時や冷たい風に当たった時、アイスなどの冷たいものを食べた時、煙を吸った時に咳が目立つ場合は、喘息の可能性があります。
●風邪をひいた時、季節の変わり目、台風などの気圧の変化でも発作が出やすくなります。
(治療)
●発作を起こした時は気管支を拡げる薬を吸ったり飲んだりします。
●発作がひどい時はステロイド薬を使用します。
●発作を起こさないために、普段から症状に合わせて吸入ステロイド薬を使用したり、アレルギーを抑える薬を飲んだりしてコントロールしていくことが大切です。
【病児保育室 ひなたぼっこ】
●住所:〒675-0151 兵庫県加古郡播磨町野添1655-1 2階
●アクセス:JR土山駅より徒歩3分
●駐車場:完備
●電話番号:078-939-6022
●WEB予約:こちらからご予約下さい